クリニック・病院における【広告の種類と対策ポイント】広告費を無駄にしない集患方法

今回は、クリニックや病院における主な広告の種類と、その広告出稿時に気をつけるべきポイントについて解説していきます。
また、どの広告方法がクリニックや病院におすすめなのか、広告代理店を選ぶ際に気をつけるべき点についても説明していますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
広告代理店を選ぶ際に特に気をつけなければいけない点について、間違った選択をしないためにもよく確認してみてください。
クリニック・病院におすすめの広告方法を確認したい方はこちらまでスキップしてください。
目次
クリニック・病院における主な広告
– WEB広告
– リアル広告
クリニック・病院における広告対策のポイント
– 広告とみなされる範囲の理解
– 広告可能事項の原則
– 広告禁止事項の遵守
– クリニックや病院が医療広告規制に抵触しないために
広告依頼時の注意点と費用対効果、おすすめの広告方法
– クリニックや病院における医療広告ガイドラインへの対策
– クリニックや病院における広告の費用対効果
– クリニック・病院におすすめの広告方法
まとめ
クリニック・病院における主な広告
クリニックや病院が情報発信をする上では、多くの種類の広告が活用されています。
広告の種類を大きく分けると「WEB広告」と「リアル広告」に分類できます。
以下、それぞれの広告にはどのような特長があるのか、また、どんな種類があるのかについて解説していきます。
WEB広告
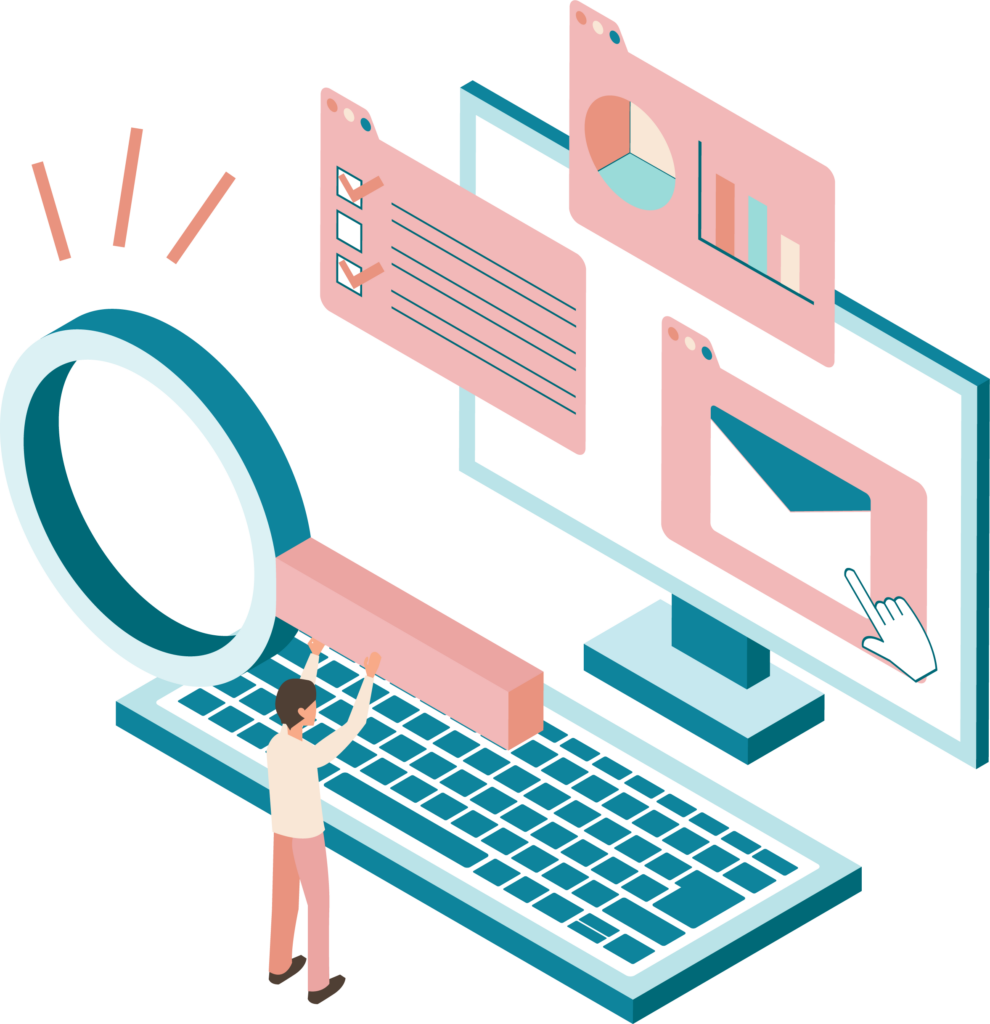
Web広告は、インターネット上のWEBサイトや、SNS、メールなどに掲載する広告を指し、「インターネット広告」、「デジタル広告」、「オンライン広告」などと呼ぶ場合もあります。
Web上で広告の設定を完了できるものがほとんどで、個人でも始めやすいプラットフォームも多く存在します。
システムを通して配信のスケジュールや予算の設定をおこなうため、リアル広告に比べ柔軟な広告配信をすることができます。
「効果測定」、「コスト計算」、「ターゲティング」などに優れていて、予算に合わせた広告出稿が可能です。
成果にもとづいて、広告の内容をアップデート・ブラッシュアップしていける点もメリットといえるでしょう。
主なWeb広告の種類は以下の通りです。
1.リスティング広告
GoogleやYahoo!といった検索エンジンの検索結果画面に表示されるテキスト広告です。
ユーザーが検索をした際に、指定したキーワードに合致すると広告が表示されます。
その広告をクリックすると費用が発生する「クリック課金型」が一般的です。
既にニーズが顕在化している(自分の欲しいものが分かっている)ユーザー に、アプローチするのに適しています。
リスティング広告の始め方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
2.ディスプレイ広告
Webサイトやアプリなどに設置されている「広告枠」に表示される広告です。
画像、動画、テキストと広告の方法は様々です。
クリック課金やインプレッション課金(表示回数に応じて費用が発生)の課金方式があります。
潜在層(まだ自分のほしいものが分かっていないユーザー)から顕在層へのアプローチや、認知度を高め興味関心を引き出すのに適しています。
アドネットワーク広告やDSP(デマンドサイドプラットフォーム)を利用して配信されることがあります。
3.SNS広告
X、Facebook、Instagram、LINEなどのSNSプラットフォーム上に表示される広告です。
使用しているプラットフォームと年齢、ライフスタイルなどでターゲットを絞り込むことで、精度の高いターゲティングが可能です。
潜在層から既存の顧客まで、幅広いアプローチに活用できます。
課金方式はクリック課金、インプレッション課金、エンゲージメント課金(いいねやシェアなどの反応に応じて費用が発生)などがあります。
4.動画広告
動画プラットフォーム(YouTubeなど)上に掲載されます。
短い時間で多くの情報を伝えられる点と、視覚的な訴求力の高さにより、認知拡大や興味関心を得るのに効果的な広告方法です。
課金方式は広告視聴単価型(CPV)などがあります。
5.リターゲティング広告
過去に自社Webサイトを訪問したことのあるユーザーに再度広告を表示する方法です。
既に興味を持っている可能性の高いユーザーにアプローチし、コンバージョン(架電やお問い合わせ)を促す効果を期待できます。
上で解説してきた広告は、システムを含む広告方法でしたが、このリターゲティング広告は、システムではなく広告のやり方・考え方にあたります。
ですので、ディスプレイ広告や動画広告などのシステムを使いおこなうことが多くなります。
6.アフィリエイト広告
「広告主」、「アフィリエイター」、「ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)」の三者で構成される広告手法です。
アフィリエイターが自身のWebサイトやSNSなどで、広告主の商材を紹介します。
紹介した商材の購入や契約などが発生した場合、ASP経由で広告主からアフィリエイターに広告費が支払われます。
費用対効果に優れ、顕在層に強く、キーワードによっては潜在層や無関心層へのアプローチも可能です。
7.ネイティブ広告
Webサイトの記事やSNSの投稿に溶け込むように表示される広告で、広告であることを意識させにくいのが特徴です。
無関心層や潜在層への認知拡大や興味喚起に適しています。
課金方式はクリック課金やインプレッション課金などがあります。
8.記事広告・タイアップ広告
Webサイト内の記事で自社の商材をPRしてもらう手法です。
広告主と媒体(WEBサイト側)が協力して作成します。
媒体の信頼性や知名度を利用できるため、読者の信頼感を獲得しやすいのがメリットです。
無関心層や潜在層へのアプローチに適しています。
課金方式はインプレッション課金などがあります。
9.純広告
特定のWebメディアの広告枠を一定期間買い取り、広告を掲載する形式です。
保証型の課金方式(期間保証型、クリック保証型など)が一般的で、幅広い層に広告を表示でき、目立つ場所に掲載できるメリットがあります。
10.メール広告
メールマガジンや広告メールに広告を掲載する手法です。
顕在層や既存顧客にアプローチするのに適しており、配信数に応じて費用が変動する配信数型課金が一般的です。
- リワード広告:広告を見たユーザーに報酬(ポイントなど)が支払われる広告で、主にスマホアプリ内で実施されます。短期間で認知度を上げることが期待できますが、ユーザーの継続率は低い傾向があります。
- デジタル音声広告:Spotifyやradikoなどのデジタル音声メディアで流れる広告です。スキップされにくく、ユーザーにストレスを与えにくいというメリットがありますが、市場はまだ成長段階にあります。
リアル広告

リアル広告とは、インターネット以外の媒体に掲載される広告です。
幅広い層に向けて露出の高い広告が打ちだせるほか、地域を絞ることで限定的かつ効果的な広告を打ちだすこともできます。
媒体の種類も多くあり、様々なターゲット層を狙うことが可能です。
ただしオンライン広告に比べて広告費用が高くなる傾向にあります。
1.テレビ広告
テレビを視聴する幅広い年齢層にリーチすることができます。
映像と音声でインパクトのある、また、繰り返し放送することで強い印象を残すことができます。
ロケーションや、CG、俳優などの要素により、制作費・放映費は高額になる傾向があります。
その分、認知度が大きく向上し、信頼性も高い広告方法といえます。
2.新聞広告
新聞自体の購読者数は減少傾向にあり、若年層は新聞を読まない方が多いことを考えると、若年層へのリーチは難しいといえます。
ただ、現在も購読している層に対しての信頼性はとても高いといえます。
また、地元紙であれば、よりローカライズされた地域住民にピンポイントで情報を届けやすいといえるでしょう。
3.駅看板・駅内ポスター
駅の利用者に、繰り返し(駅の利用時の度に)情報を伝えられるのがメリットです。
大きな看板やポスターであれば、視認性が高く、インパクトも強く、印象に残りやすいです。
設置する場所や期間によって、費用が大きく変動し、最初の持ち出し金額として数十万~数百万単位で考えておく必要があります。
4.電車内広告
通勤・通学客に、長時間(電車に乗っている間)情報を伝えられます。
特定の路線を利用する層に、効率的にリーチできる点がメリットです。
昨今では、現物のポスターに加え、電車内に設置してあるモニターにより、動きのある広告を展開できるようにもなっていきました。
5.バス広告
地域住民に、密着した情報発信ができます。
移動中の人々に、視覚的に訴求できるポスター型のものと、社内アナウンスで「聴く広告」をおこなうこともできます。
6.タクシー広告
特定の地域や層に、ピンポイントで情報を届けられます。
タクシーを多く利用する層(ビジネスマンや富裕層)へのリーチが期待できるのがポイントです。
7.電柱看板・街中看板・街中ポスター
通行人に、繰り返し情報を伝えられます。
24時間、情報を発信できるのがメリットです。
地図やクリニック・病院までの道のり・距離などを掲載するのも一般的な活用方法です。
8.デジタルサイネージ
動画やアニメーションで、視覚的に訴求できます。
タイムリーな情報発信や、インタラクティブな広告も可能です。
設置費用や運用費用が高額になる場合があります。
広告とは少し異なりますが、院内のモニターに「お知らせ」や「注意事項」などを表示させるシステムもあり、初期費用と手ごろなシステム使用料のみで運用できます。
9.チラシ・DM
地域住民や特定の層に、直接情報を届けられます。
QRコードを設置し、WEB予約につなげたり、来店促進につなげやすいのがメリットです。
配布方法や配布エリアなどターゲティングの仕方により、得られる効果が大きく変動します。
リアル広告の中では比較的ローコストで広告展開できるのも魅力の一つです。
クリニック・病院における広告の対策ポイント

クリニックや病院が広告を出稿するにあたって注意すべき点は多岐にわたります。
しかし、最も重要なことは、「医療法および医療広告ガイドライン」を遵守することといえるでしょう。
この規制は、「患者が不適切な広告によって不利益を被ること」を防ぎ、「適切な医療選択」を支援するために設けられています。
以下に、特に注意すべき点をまとめました。
広告とみなされる範囲の理解
従来の看板やチラシだけでなく、クリニックや病院のホームページ、SNSアカウント、アフィリエイターの記事、口コミサイト、ポータルサイトなども医療広告の規制対象となりました。
ウェブサイトの内容についても、医療広告ガイドラインに沿った適切な情報提供が求められるようになっています。
広告可能事項の原則
原則として、医療法で定められた広告可能な事項(医療法第6条の5第3項に列挙)以外は広告できません。
例えば、医師または歯科医師である旨、診療科名、名称、電話番号、所在地、診療時間などが該当します。
割引やキャンペーンなどといったことは、医療広告規制に抵触し、行政からの指導や罰則の対象となります。
広告禁止事項の遵守
以下の広告は厳しく禁止されています。
1.虚偽広告
事実と異なる内容や根拠のない情報を掲載すること。術前術後の写真を加工・修正して掲載することも該当します。
2.比較優良広告
他の医療機関と比較して自院が優れていると示唆する広告。「日本一」「No.1」「最高」といった最上級表現や、著名人との関係性を強調する広告も該当する可能性があります。
3.誇大広告
事実を誇張したり、誤解を招くような表現を用いたりする広告。科学的根拠に乏しい情報を提示することも含まれます。都道府県が認める場合などを除き、「〇〇センター」といった名称も誇大広告とみなされることがあります。
4.公序良俗に反する内容の広告
わいせつ・残虐な画像や差別を助長する表現など。
5.治療等の内容や効果に関する体験談の広告
患者さんの主観的な体験談や口コミを広告として利用すること。ただし、医療機関からの依頼に基づかない個人のSNS投稿などは広告とみなされない場合があります。
6.治療等の内容・効果についての、治療等の前後の写真等の広告
患者を誤認させる可能性のあるビフォーアフター写真の無条件掲載は禁止されています。一定の条件(通常必要とされる治療内容、費用、リスクなどの詳細な説明を付記するなど)を満たす場合は掲載可能な場合もあります。
7.他法令に抵触する広告
医薬品医療機器等法、健康増進法、景品表示法、不正競争防止法などの関連法規に違反する広告。
8.品位を損ねる内容の広告
費用を過度に強調したり、治療と直接関係のないプレゼントを謳ったりする広告。
9.広告可能事項の限定解除
一定の条件(患者が自ら求めて情報を入手する場合、問い合わせ先を明示する場合、自由診療に関する詳細な情報提供を行う場合)を全て満たすウェブサイトなどに限り、広告可能な事項以外の情報も記載できる限定解除の制度があります。
ただし、禁止事項は限定解除の対象外です。
リスティング広告自体の文章や画像は原則として限定解除できません。
クリニックや病院が医療広告規制に抵触しないために
1.ウェブサイトの適切な運用
ホームページは、クリニックの基本情報や診療内容を正確に伝える重要なツールです。SEOにより検索エンジンで上位表示されるように努めることも重要ですが、医療広告ガイドラインを遵守した内容である必要があります。
2.SNSの適切な活用
SNSは患者さんとのコミュニケーションや情報発信に有効ですが、情報発信する際には医療広告ガイドラインの内容を遵守する必要があります。
3.リアル広告の適切な活用
チラシや看板などのリアル広告も誘引性・特定性がある場合は医療広告とみなされ、医療広告ガイドラインの規制を受けます。
4.罰則の存在
医療広告ガイドラインに違反した場合、行政指導、中止命令、是正命令などの措置が取られ、悪質な場合には告発・行政処分、公表、さらには懲役や罰金、病院または診療所の開設許可の取り消しといった重い罰則が科される可能性があります。
5.専門家への相談
医療広告の規制は複雑で、判断に迷う場合も多いため、広告制作や出稿にあたっては、医療広告ガイドラインを熟知した専門家(弁護士、広告代理店など)に相談することを強く推奨します。
広告は、クリニックや病院にとって重要な情報発信・集患の手段ですが、医療という特性上、患者さんの安全と適切な医療選択を最優先に考慮し、関連法規やガイドラインを遵守して行う必要があります。
また、医療広告ガイドラインについてはこちらの記事でも詳しく解説していますので、興味があればのぞいてみてください。
広告依頼時の注意点と費用対効果、おすすめの広告方法
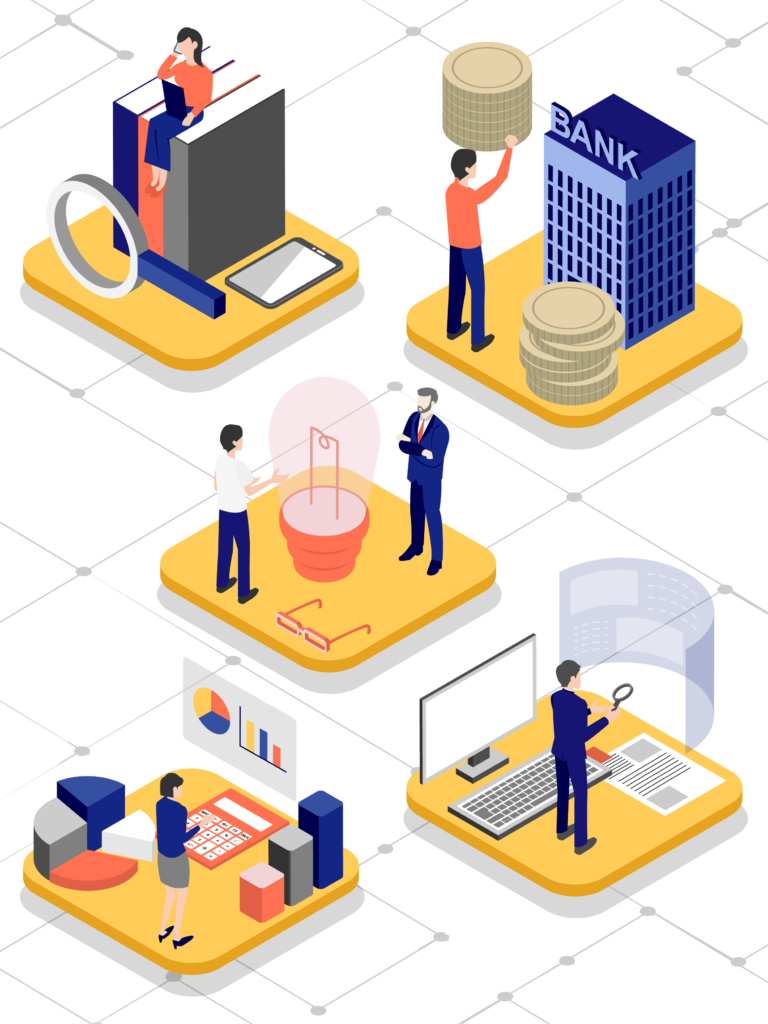
さて、多くの広告方法について解説してきましたが、結局どの広告やどういった広告代理店を選択するのが、クリニックや病院に合った方法なのでしょうか。
「医療広告ガイドラインへの対策」と「費用対効果」の面から、クリニックや病院に適切な広告について考えていきたいと思います。
クリニックや病院における医療広告ガイドラインへの対策
WEB広告にせよ、リアル広告にせよ、避けては通れないのが、上で述べた医療広告ガイドライン(医療広告規制)の遵守です。
どのような表現が広告規制に抵触するのかを知っていることは、広告を出稿する上では必須の要件となります。
規制について知識が無かったり、中途半端な知識で広告運用をおこなうと、行政指導や行政処分、罰則などのペナルティが科される可能性があります。
1.医療広告規制についての知識を持つ専門家に依頼することがおすすめ
クリニックや病院の医師や職員が、医療広告規制を勉強して対策することも可能ですが、医療広告ガイドラインやそれに付随したQ&Aなどの内容を理解するのは相当に骨が折れるといえるでしょう。
また、規制は日々アップデートし、常に最新の情報を把握しておく必要もあります。
クリニックや病院の日々の業務も含めて考えると、こうした勉強コストをかけるより、ガイドラインの知識を持った専門家に広告運用を依頼する方が良いと考えられます。
2.医療広告ガイドラインの知識をもっているかの判断方法
この広告規制には資格などがありません。
ではどうやって、この規制の知識があるかどうか判断すればよいでしょうか。
知識がある企業には、必ずWEBサイト(ホームページ)内に「医療広告ガイドラインを遵守している」ことが記載されているはずです。
それは、このガイドラインが、広告を運用するにあたって非常に重要だからです。
前の項にも記載しましたが、医療広告ガイドラインを守らなかった場合、行政指導や処分、罰則などのペナルティを科されてしまいます。
医療について広告を扱う場合は、医療広告ガイドラインの遵守は避けては通れない要素となっています。
もし、広告運用を業者に依頼したいと考えた場合、企業または個人のWEBサイトやSNSプロフィールなどから「医療広告ガイドライン」についての記載があるか確認してみてください。
記載がない場合は、広告運用はおこなっているが、「医療広告ガイドライン」についての知識がない、あるいは医療の情報を持っている広告代理店などではない可能性があります。
広告運用を依頼する場合は、必ず、知識をもつ企業や個人に依頼することをおすすめします。
クリニックや病院における広告の費用対効果

クリニックや病院における広告の費用対効果は、かけた予算に対してどれほどの集患につながったかで図ることができます。
ここでは、日頃よく目にする、リスティング広告、チラシ広告、駅看板広告で、大まかな費用や効果について比較してみたいと思います。
1.リスティング広告にかかる予測費用
リスティング広告は、GoogleやYahoo!での検索時に、検索結果の上部に表示される広告です。
本当に最少の金額であれば1万円以下からでも運用をおこなうことが可能です。
ただ、一定の成果(お問い合わせやWEB予約)を獲得したいなら、数万円単位で予算を考える必要があります。
広告代理店に依頼する場合、初期設定費用として数万円~十数万円かかり、毎月の運用費は広告費に合わせて手数料がかかる予算感となります。
リスティング広告は、リアル広告と比較すると運用予算の幅が広く、低い予算からでも始められることが魅力です。
〇初期費用
5万円~10万円
〇月額運用費
3万円~
2.チラシ広告にかかる予測費用
チラシ作成の費用は、以下の要素によって大きく変動します。
- 印刷部数
- 用紙の種類
- 用紙のサイズ
- カラー/モノクロ
- 両面/片面
仮に、A4サイズ、片面カラーとした場合、一般的には1万部の印刷で数万円程度になることが多いです。
また、ポスティングをおこなう場合、1枚あたり数円~数十円程追加で費用がかかります。
チラシのデザインから依頼する場合はこの限りではありませんが、リアル広告の中では比較的低予算で広告ができる方法になります。
※A4片面カラー、1,000枚印刷、ポスティングありの場合
〇デザイン費
3万円~5万円
〇印刷代
2,000~3,000円
〇ポスティング費用
3,000~12,000円
3.駅看板広告にかかる予測費用
駅看板広告の作成費用は、以下の要素によって大きく変動します。
- 駅の規模と乗降客数
- 看板のサイズと種類:
- 看板の種類(大型の看板や電飾看板は高額)
- 契約期間(長期ほど割引が適用される傾向)
- 掲出場所(改札付近やホームなど、目立つ場所は高額)
駅や看板のサイズによって大きくことなりますが、一般的な相場としては数万円~数百万円/月を考えておく必要があります。
〇費用
東急 渋谷駅、縦1m×横1.6m、210万円 / 年
広告の即時性
ここでの即時性とは、運用開始までのスピード感や広告の変更・修正に対しての対応スピードで考えてみたいと思います。
どの媒体に対してもターゲティングは必要になるため、それは除外したとして、リスティング広告、チラシ広告、駅看板広告を比較すると次のようになります。
- リスティング広告:設定に数日ほど。
- チラシ広告:チラシのデザインで数日~数週間程度。部数や仕様にもよるが印刷に1週間~2週間ほど。ポスティングする場合は、更に1週間ほど。
- 駅看板広告:デザインを含め、早くても1~1.5ヶ月ほど。
広告成果の計測方法
1.広告成果集計のポイント
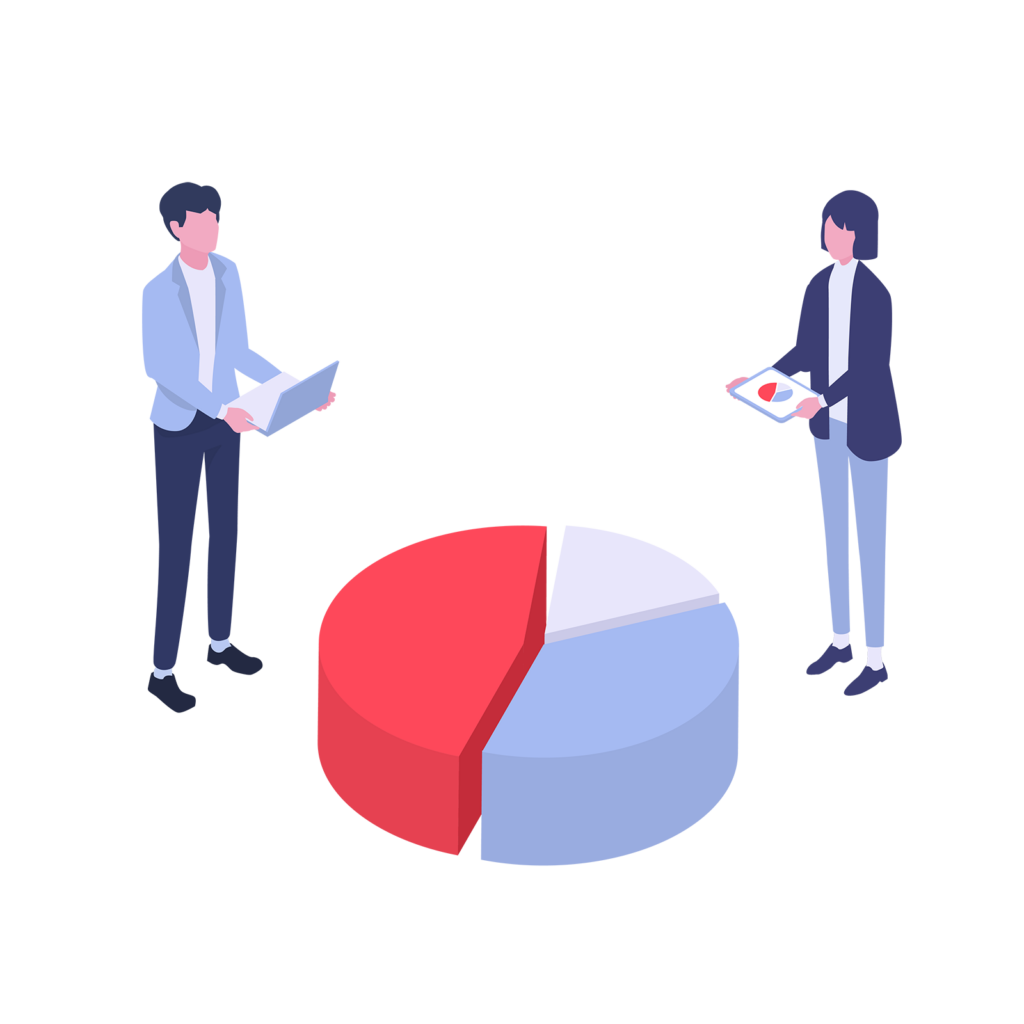
広告の目的を明確にすることが重要です。
その目的に合わせ、地域や期間を区切り、広告をおこなう前と比較することも大切になってきます。
広告の方法には長所と短所があり、その特性を理解して活用することが、もっとも有効な手だてになりえます。
2.リスティング広告の成果集計
リスティング広告は、詳細なデータ計測が可能です。
- インプレッション数:広告が表示された回数を計測します。
- クリック数:広告がクリックされた回数を計測します。
- クリック率(CTR):広告のクリック数をインプレッション数で割った割合を計測します。
- コンバージョン数:広告をクリックしたユーザーが、Webサイト上で目標とする行動(問い合わせ、購入など)を完了した回数を計測します。
- コンバージョン率(CVR):コンバージョン数をクリック数で割った割合を計測します。
リスティング広告の最大の特長としては、成果が数値で分かるという点といえるでしょう。
広告が表示させた回数およびその広告がクリックされた数が分かり、更にそのクリックの中で目的の成果に到達した数も計測できるのが大きなメリットです。
3.チラシ広告の成果集計
チラシ広告の効果測定は、配布方法や目的によって異なりますが、いくつかのパターンで考えてみたいと思います。
- 問い合わせや来店数の増加:チラシ配布前後の問い合わせ数や来店数を比較します。
- アンケート調査:来店者や問い合わせ者にアンケートを実施し、チラシを見たかどうか、どのような印象を受けたかなどを調査します。
- Webサイトへのアクセス数:チラシに専用の問い合わせURLやQRコードを記載することで効果測定します。
- コールトラッキング:チラシに表示する電話番号を通常のものとは別に、広告効果測定用の電話番号を掲載します。この広告効果測定用の電話番号にかかってきた件数を計測することで、チラシを見た人がどれくらい電話をかけてきたのか計測することができます。
4.駅看板広告の成果集計
駅看板広告は、認知度向上を目的とする場合が多く、効果測定の方法としてはチラシと同様になります。
- 問い合わせや来店数の増加:駅看板掲示前後の問い合わせ数や来店数を比較します。
- アンケート調査:駅利用者や周辺住民にアンケートを実施し、駅看板を見たことがあるか、どのような印象を受けたかなどを調査します。
- Webサイトへのアクセス数:駅看板に専用のWebサイトのURLやQRコードを記載し、通常のWebアクセスとは別の数値として計測します。
クリニック・病院におすすめの広告方法
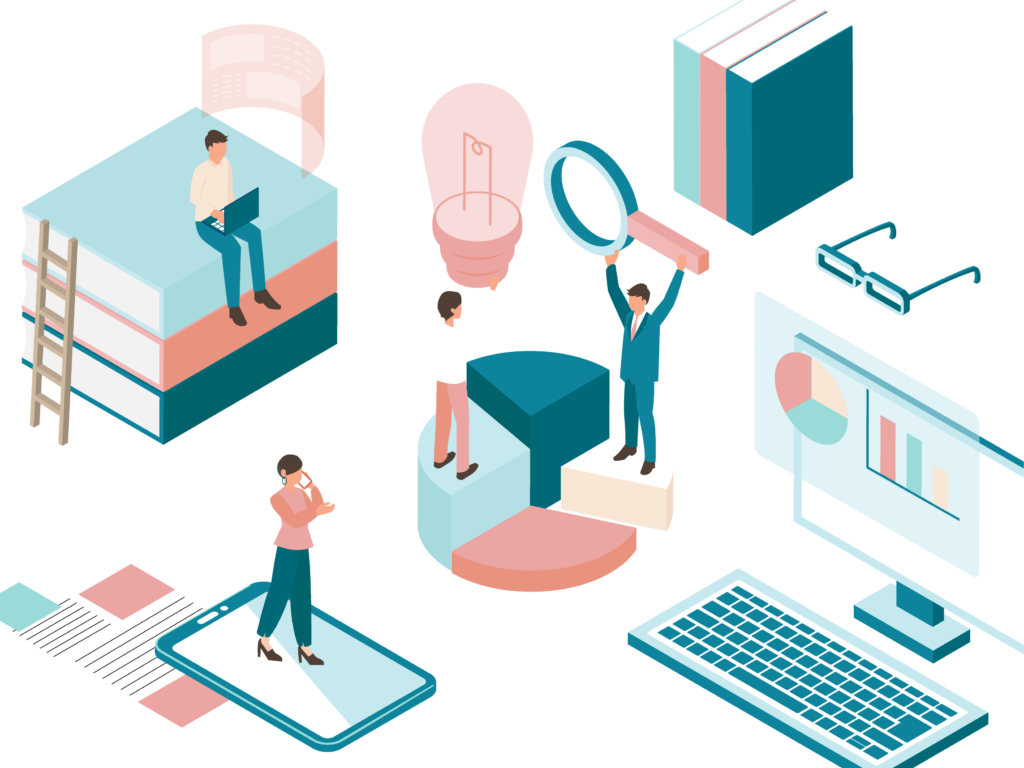
費用面の柔軟さや広告出稿までのスピード感ではリスティング広告(Web広告)がすぐれています。
対して広告を見た人への訴求力はチラシや看板のようなリアル広告がすぐれているといえると思います。
近年では、SNS広告や動画広告など、新しいWeb広告も登場しており、これらの手法も積極的に活用することで、より多角的な広告戦略を展開できるようになってきました。
予算に余裕があれば、Web広告とリアル広告を組み合わせた、クロスメディア戦略が効果を発揮することでしょう。
しかし、限られた予算の中で広告を展開する場合には、より「成果が分かりやすく」、「費用対効果が高い方法」を選択しなければなりません。
もし、強いてクリニックや病院が優先的におこなうべき広告方法を一つだけあげるとするならば、「リスティング広告」がおすすめです。
1.なぜリスティング広告がおすすめなのか
クリニックや病院に対して、なぜリスティング広告が一番おすすめといえるかというと、次の理由があげられます。
リアル広告と比較していうならば、
- 低予算(数万円)から高予算まで、幅広く対応できます。
- 広告開始までの短さに加え、リアル広告ではほとんどできない広告内容の変更についても柔軟に対応できます。
- 成果(表示、クリック、電話タップ、WEB予約など)が数値として計測でき、かけた費用に対して、効果が明確に分かります。
例えば、かけた予算が「10万円」、「Web予約ボタンを押した数」が100件であれば、1,000円で1ユーザー(≒患者)を獲得できたことになります。
WEB広告内の他の広告方法と比較するならば、
- 多くの人が日常的に活用する、検索エンジン(GoogleやYahoo!)といったプラットフォームで広告を展開できるのがポイントです。
- SNSやYouTubeといった動画のプラットフォームも多くのユーザーが使っていますが、SNSを使うユーザーでも「ブラウザ検索(GoogleやYahoo!での検索)」はおこない、「動画」を見るユーザーでも「ブラウザ検索」はおこなうことが多いと予想されます。このように、どんな趣味趣向を持つユーザーでもおこなうブラウザ検索は、Web広告の中でもトップのユーザーボリュームを誇るプラットフォームといえるでしょう。
- 他の広告をおこなうにしても、Web広告をおこなうならば、まず初めにおこなっておくべき広告だといえるからです。理由は上の項目と同じになりますが、多くのユーザーが日常的におこなう「ブラウザ検索」というプラットフォームは他の広告方法よりも圧倒的にユーザーのボリュームが多いといえます。
- このリスティング広告をおこない、その成果を見てから「SNSを使っていそうなユーザー層が多そうだから」SNS広告を検討し、「ビジネスマンがユーザー層に多そうだから」記事広告・タイアップ広告を検討するといった、広告戦略の中心になる存在だといえます。
2.どんな広告代理店がおすすめなのか
クリニック・病院における、広告代理店の選定ポイントはいくつかあります。
- クリニックや病院の広告運用実績があるかどうか
- 医療広告ガイドラインについて、企業ホームページ内に記載があるかどうか
- 検索エンジンや、広告運用の知識をもっているかどうか
- 広告費用が明確かどうか
これらのポイントをおさえている広告代理店として「メディココンサルティング」をおすすめします。
一つ目の「クリニックや病院の広告運用実績があるかどうか」は言わずもがなですが、一般企業を相手にしているだけではなく、クリニックや病院、医療関連の知識があるのか、それに対してのノウハウを持っているかが重要だからです。
診療科目や一般的な疾患や施術方法の知識を持たない広告代理店を選択しては、間違った情報を広告してしまう原因となり、ユーザーに対してマイナスイメージを持たれてしまいます。
二つ目の「医療広告ガイドラインについて、企業ホームページ内に記載があるかどうか」についても同様です。
医療の基本的な知識に加え、「クリニックや病院が広告する上で守らなければいけないこと」についても、広告をおこなう企業は把握しておかなければいけません。
ガイドラインに抵触した表現を使ったため、「行政から指導・制裁を受けた」り、「ユーザーに虚偽や誇大な広告をしてしまったり」、「競合クリニックや病院から訴えられてしまったり」など、様々な問題が出てくることは、極力避けなければいけないからです。
三つ目の「検索エンジンや、広告運用の知識をもっているかどうか」では、検索エンジン対策(SEO)の知識や実績、広告運用の知識を確認します。
SEOは、狙ったキーワードで検索結果に表示させるために検索エンジンの仕組みを把握していることが重要です。
SEOの実績としては、その企業の作成・管理しているWebサイトが検索結果に表示されることや、または、作成件数が多いこと(ノウハウがある)も判断材料になると思います。
広告運用の知識に対してはどのように判断すれば良いのかというと、「Google広告パートナー」資格を有しているかどうかが一つの判断材料になります。
「Google広告パートナー」は、Googleが広告運用面での知識や技術を認めた企業・個人に付与する資格になります。
Google広告における最新情報やターゲティングの仕方を把握し、Webによる筆記テストもクリアしなければならない資格となっています。
この資格を持っていることは、検索エンジンの圧倒的シェアNo.1であるGoogleに、広告運用において認められたことを意味しています。
これらを前提条件とし、広告費用が適正で、料金テーブルがわかりやすいことも重要な要素です。
四つ目の「広告費用が明確かどうか」では、費用が安いことよりも、明確であることに注意してほしいと考えこの文言にしています。
初めて広告運用を開始する場合、どうしても費用が安いことに注視してしまうこともあるかと思いますが、それよりも重要なのが、「この費用でどこまでやってくれるのか、どれほどの成果を見込めるのか」ではないでしょうか。
広告は、展開する地域や科目・施術により、方法が大きく変化してきます。
ですので、広告代理店として「成果はこれくらい見込めます」と初めに見込みを出すことは大変難しいのが現実であることは理解しておく必要があります。
ただ、希望の広告地域や、狙いたいキーワードなどをヒアリングした後であれば、ある程度の見込み成果を出すことも可能になってきます。
メディココンサルティングでは、クライアントの要望をヒアリングした後、どの程度の成果が見込めるのかをクライアントに提出します。
また、広告運用の手数料についても明瞭です。
こういった料金形態が透明であることは、広告を依頼する側としても安心材料になると思います。
これら四つのポイントがクリアしている広告代理店として、「メディココンサルティング」をおすすめさせていただきました。
メディココンサルティングは、医療専門のコンサルティング会社であり、医療広告ガイドラインについての記載がHP上にあり、制作実績も4,500件以上あります。
Google広告パートナーを保持しており、広告代理店として知識・技術を認められているといえます。
もし、確認してみたい場合は、以下ページよりお問い合わせしてみてください。
まとめ
広告の種類と広告戦略のポイントをみてきましたが、用途に合った広告方法を選択することが何よりも重要だということが分かるかと思います。
WEB広告にもメリットとデメリットがあり、同様にリアル広告にもメリットとデメリットがあります。
クリニックや病院における広告の種類と対策のポイントとして、「WEB広告」と「リアル広告」について解説してきました。
この記事を広告を出す際のご参考にしていただければと思います。
限られた予算の中で広告を配信する場合は、「成果が分かりやすいこと」と「費用対効果が高いこと」が重要という理由から「リスティング広告」がおすすめだとお伝えしました。
また、クリニックや病院において、広告代理店の選定ポイントとしては以下をあげています。
クリニックや病院の広告運用実績があるかどうか
医療広告ガイドラインについて、企業ホームページ内に記載があるかどうか
検索エンジンや、広告運用の知識をもっているかどうか
広告費用が明確かどうか
これらのポイントをおさえている広告代理店の一例として「メディココンサルティング」をおすすめさせていただきました。
以上参考になれば幸いです。